子どもたちがAI時代に身につけたい能力

 skymother
skymotherこのブログでは、保健師が子育ての情報を発信しています。
AI時代でも大丈夫!わが子の「未来を生き抜く力」、おうちで育む5つのヒント
「AIに仕事が奪われるって本当?」「うちの子の将来、どうなっちゃうんだろう…」
最近、そんなニュースを見かけるたびに、子どもの未来がちょっぴり心配になりますよね。実際、子育て中のママやパパの約8割が、私たち親の時代とは世の中が大きく変わることへ不安を感じているそうです 。
AIはとっても便利ですが、頼りすぎると「自分で考える力」や「新しいものを思いつく力」が弱くなってしまうかも、という声も 。
でも、心配しすぎなくても大丈夫!特別なことをしなくても、毎日の暮らしの中に、これからの時代に本当に必要となる「人間ならではの温かい力」を育むヒントはたくさん隠されています。
今回は、AI時代だからこそ大切にしたい「5つの力」と、おうちでできる簡単な関わり方のコツをご紹介します。
1. 「それってホント?」と考える力(クリティカルシンキング)
情報をそのまま信じるのではなく、「どうしてかな?」「本当にそうかな?」と自分の頭で一度考えてみる力のことです。
AIは色々なことを教えてくれますが、時々、間違った情報や偏った意見を、さも本当のことのように話すことがあります 。そんな情報の波に流されず、自分の考えをしっかり持つことが、これからの時代にはとても大切になります。
おうちでできる簡単アクション
- 魔法の言葉は「どうして?」:子どもが何かを話してくれた時、「なぜ?」と詰問するのではなく、「へぇ!どうしてそう思ったの?」と優しく聞いてみましょう 。自分の考えを話すのが楽しくなります。
- 「事実」と「意見」探しゲーム:「今日の給食はカレーだった(事実)」と「今日のカレーは辛かった(意見)」のように、日常の会話の中でどっちかな?とクイズを出し合うと、物事を正確に見る目が育ちます 。
- 絵本の続きを読む:読み聞かせの途中で「この後、どうなると思う?」と問いかけてみましょう。物語の続きを想像することで、考える力がぐんぐん伸びます 。


2. 「もっとこうしたら面白いかも!」とひらめく力(クリエイティブな思考)
AIが思いつかないような、ユニークで新しいアイデアを生み出す力です。
AIの得意技は、すでにあるたくさんの情報を組み合わせて新しいものを作ること 。でも、本当にゼロから何かを生み出したり、人の気持ちに寄り添った温かいアイデアを考えたりするのは、やっぱり人間の得意分野です 。これからの時代、この「ひらめき」こそが、わが子の大きな武器になります。
おうちでできる簡単アクション
- 五感をフル活用!:粘土遊びやブロック遊び、お絵描きやダンスなど、手や体、心をたくさん使って表現する遊びを一緒に楽しみましょう。本物の体験が、豊かな感性を育てます。
- 結果より「頑張り」を褒める:「上手にできたね!」だけでなく、「いろんな色を使ったね!」「途中で諦めないで頑張ったのがすごいね!」など、工夫した点や努力の過程を具体的に褒めてあげましょう 。失敗を恐れずに挑戦する心が育ちます。
- 「何もしない時間」をプレゼント:あえて予定を入れず、子どもが自由に空想したり、ボーッとしたりする時間も大切です。そんな「余白」から、子ども自身の「やりたい!」が生まれてきます 。
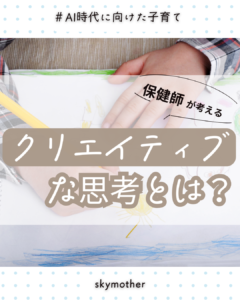
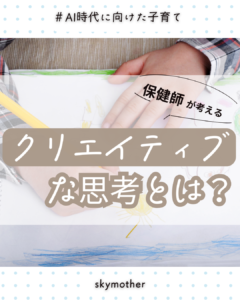
3. ネットの世界と上手に付き合う力(デジタルリテラシー)
スマホやタブレットを上手に使いこなしながら、インターネットの世界に責任を持って参加する力のことです。
これまでは「危ないからダメ!」と制限することが中心でしたが、これからはデジタル社会の「良き市民」として、ルールを守りながら上手に活用し、社会をより良くしていく積極的な姿勢が求められます 。
おうちでできる簡単アクション
- 合言葉は「玄関に貼れることだけ」:「お家の玄関ドアに貼られても恥ずかしくないことだけ、ネットにも書いていいんだよ」と教えてあげましょう。不特定多数の人が見るネットの世界の感覚が、子どもにも分かりやすく伝わります。
- ルールは親子で一緒に作る:一方的にルールを押し付けるのではなく、「どうしてこのルールが必要だと思う?」と話し合いながら、親子で納得できるルールを決めましょう 。自分で決めたルールなら、子どもも守ろうという気持ちになります。
- ママ・パパがお手本に:食事中や子どもと話している時はスマホをそっと置く、SNSでは人を傷つける言葉を使わないなど、親が良いお手本を見せることが一番の教育になります 。
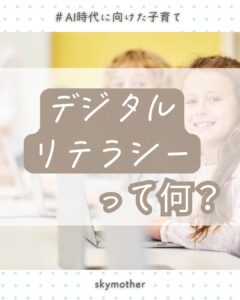
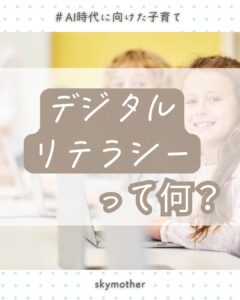
4. 「気持ちを伝え、心をかよわせる力」(コミュニケーションと協働)
相手の話をしっかり聞き、自分の気持ちを上手に伝え、みんなと協力して何かを成し遂げる力です。
AIと話す機会が増えると、表情や声のトーンから相手の気持ちを察する経験が少なくなるかもしれません 。でも、AIにはできない、人の心の機微を理解し、共感し、励まし合うような温かいコミュニケーションこそ、これからますます価値が高まります。
おうちでできる簡単アクション
- あいさつと「ありがとう」から:親が普段から「おはよう」「ありがとう」「ごめんね」をたくさん使うことで、子どもは自然にコミュニケーションの基本を学んでいきます 。
- 「聞く」時間を大切に:食事の時間だけでも、スマホはテーブルの隅に置いて、子どもの目を見て「うん、うん」と話を聞いてあげましょう。「ママはちゃんと話を聞いてくれる」という安心感が、子どもの自己肯定感を育みます 。
- 気持ちに「名前」をつけてあげる:子どもがうまく言葉にできないモヤモヤした気持ちを、「それは悔しいっていう気持ちだね」「がっかりしたんだね」と代弁してあげましょう 。自分の気持ちを客観的に理解し、表現する練習になります。


5. 「失敗もへっちゃら!」なしなやかな心(柔軟性と適応性)
うまくいかないことや、予期せぬ変化が起きても、それに合わせて自分の考えややり方をしなやかに変えていける力です。
これからの社会は、変化するのが当たり前。今日覚えたことが明日には古くなるかもしれません 。そんな時代だからこそ、一つのやり方にこだわらず、転んでも「さあ、次!」と立ち上がれる「心のしなやかさ(レジリエンス)」が大切になります。
おうちでできる簡単アクション
- ママ・パパも学びを楽しむ姿を:親自身が新しいことに挑戦したり、楽しそうに本を読んだりする姿は、子どもにとって最高の刺激になります 。「学ぶって楽しいことなんだ」というメッセージが自然と伝わります。
- 小さな「できた!」を積み重ねる:親が先回りして助けるのではなく、少しだけ難しいことに挑戦させてみましょう。自分で考えて乗り越えた経験が、「自分ならできる!」という本物の自信につながります。
- 子どもに「選ばせて」みる:「今日着る服、どっちがいい?」「夕飯はご飯とパン、どっちにする?」など、日常のささいなことでOK。自分で選んで決める経験が、主体性を育てます 。
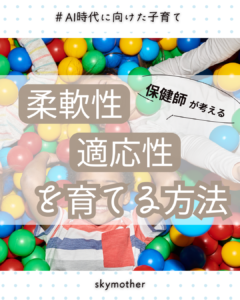
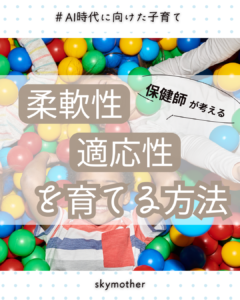
まとめ:ママの笑顔が、子どもの未来を照らす一番の光
AI時代と聞くと、なんだか難しく考えてしまいがちですが、大切なのはとてもシンプル。
AIを怖がるのではなく、便利なパートナーとして上手に付き合いながら、私たち人間にしかできない「温かい心」や「しなやかな発想」を育んでいくことです 23。
今回ご紹介した5つのヒントは、すべて日々の暮らしの中で、ママやパパが少し意識するだけで始められることばかり。
何より大切なのは、子どもと向き合うママ自身が笑顔でいること。その安心感が、子どもがのびのびと未来へ羽ばたくための、一番のエネルギーになるはずです。



最後までお読みいただきありがとうございました。
私の発信が少しでもお役にたてると嬉しく思います。
褒め言葉100選」プレゼント中
今日から使える!「子どもの自己肯定感を育てる褒め言葉100選」PDFリストを無料でプレゼント中です!
- 努力・工夫を褒める言葉
- 感謝・共感を伝える言葉
- 自主性を引き出す言葉
- 存在そのものを肯定する言葉
など、具体的な声かけを100個、見やすいリストにまとめました。
冷蔵庫に貼っておけば、忙しい毎日でも、もう言葉に迷いません。
今すぐ下のボタンから公式LINEに登録して、「プレゼント」とメッセージを送るだけで受け取れます。
